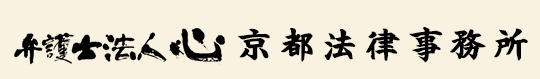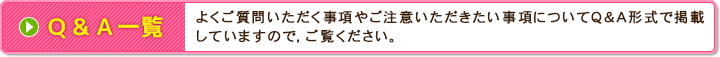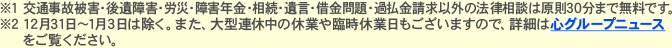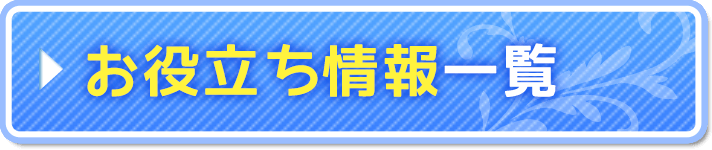遺留分を請求する場合の流れ
1 消滅時効の期間の満了前に請求する
遺留分侵害額請求権については、短期の消滅時効が定められており、消滅時効の期間の満了の前に請求をする必要があります。
この消滅時効の起算点は、自らの遺留分が侵害されたことを知ったときです。
一般的には、遺言書の内容を見て、自らの遺留分が侵害されていることを知るということが多いでしょうから、被相続人が死亡したことに加えて、遺言書の内容をも知ったときが消滅時効の起算点になることが多いです。
ただし、相続財産の内容を正確に把握しておらず、遺言書の内容も、その内容だけからは遺留分を侵害しているかが判然としない場合には、相続財産の概要を把握したときが起算点になることもあるでしょう。
消滅時効の期間は1年とされていますので、この起算点から1年以内に請求をする必要があります。
確実に請求をしたということを証拠に残しておく必要がありますので、実務上は、遺留分の請求を内容証明・配達証明付きの郵便による書面ですることが一般的です。
この請求にあたっては、具体的な金額まで提示する必要がなく、遺留分侵害額の請求をする意思を表示すれば足りるとされています。
ただし、いったん遺留分の請求をしたとしても、これは一般の債権として、さらにそこから5年の消滅時効にかかる可能性がありますので、注意しましょう。
なお、相続開始から10年という期間制限もありますので、こちらにも注意が必要です。
2 遺留分の侵害額を計算する
相手方に遺留分を請求するためには、自分がいくらの請求ができるのかを確認する必要がありますので、遺留分の侵害額を計算することになります。
まずは、相続人を確認したうえで、自らの遺留分の割合を確認します。
相続人がはっきりしない場合には、戸籍を取得して確認する必要があります。
次に、亡くなった方の遺産にどのような財産があったのかを確認しましょう。
不動産については、亡くなった方の名寄帳や固定資産税の評価証明書、登記情報を取り寄せることで確認ができます。
預貯金については、金融機関に残高証明書や取引履歴を発行してもらうことで内容の把握ができます。
その財産の中に不動産や株式などの評価が必要な財産がある場合には、その財産を評価する必要もあります。
亡くなった方の遺産のほかにも、一定の生前の贈与も遺留分の算定の対象になります。
不動産の登記情報や、預貯金の取引履歴、亡くなった方の日記などから、生前贈与の情報と証拠を集めるようにします。
遺留分の算定の基礎となる財産の内容がはっきりしたら、自らの遺留分侵害額を計算します。
なお、自分が生前に被相続人から受け取っている財産がある場合や、被相続人の負債を負担した場合には、その調整も必要です。
また、請求の相手先が複数となる可能性がある場合、遺留分の請求先や内容には順位が決められていますので、このルールにしたがって、それぞれの相手先への請求額を計算する必要があります。
3 協議がまとまらなければ裁判手続きをとる
相手方への請求額が決まったら、相手方に遺留分侵害額を支払ってもらうように請求します。
1で述べたように、請求額を明らかにしてから請求書を送る場合もありますし、まずは額を明らかにせずに請求書を送る場合もあります。
こちらの請求額に対して、相手がすんなり支払ってくれれば、それで完了となります。
しかし、ほとんどの場合は相手方からも反論がありますし、当方との考え方の違いがあることが明らかになることが多いです。
そのような場合には、双方の考えを合理的に説明し、考え方の違いを埋めていく協議が必要です。
そこで、遺留分侵害額の支払いに関する合意ができたのであれば、後日の争いを避けるために遺留分侵害額に関する合意書を作成しておきましょう。
合意書の内容については、遺留分侵害額の内容や、その支払方法などが主な記載内容になります。
この合意書は、相続税の申告の必要があり、申告や更生が必要な場合にも税務署に提出するため、作成しておく必要があります。
他方、このように、相手方と協議をしても合意に至らないこともあるでしょう。
協議がまとまらない場合には、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることが原則になります。
調停とは、裁判所において、当事者間で話し合うための手続きであり、裁判所の調停委員会からの助言や調整を受けながら、当事者間で遺留分に関する合意ができないかを話し合っていくことになります。
そのような調停によっても合意ができない場合には、通常の訴訟を提起して、遺留分侵害額の支払いを請求していくことになります。
審理の過程で和解が成立することもありますが、最終的な結論は、裁判官が証拠に基づいて決めることになります。
遺留分の請求について弁護士に相談したほうがよい理由 相続放棄をお考えの方へ